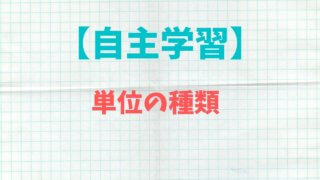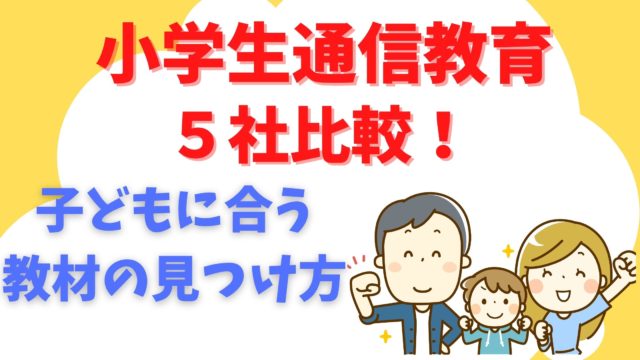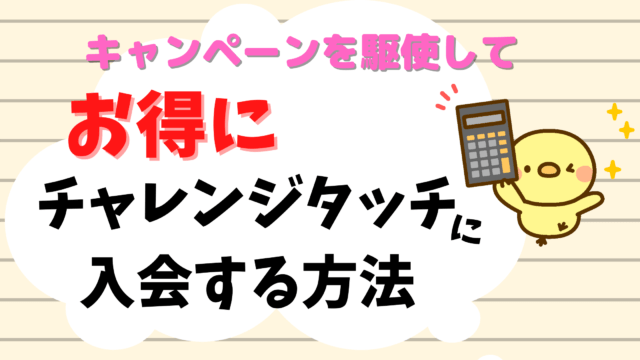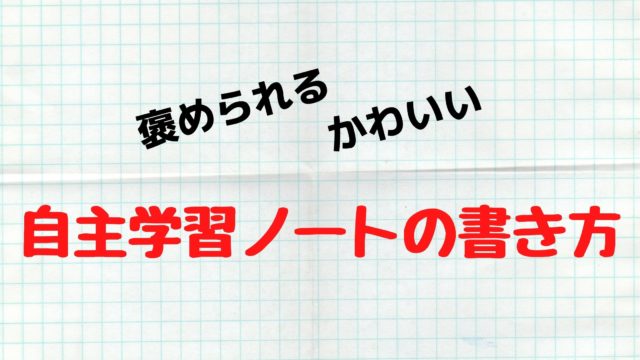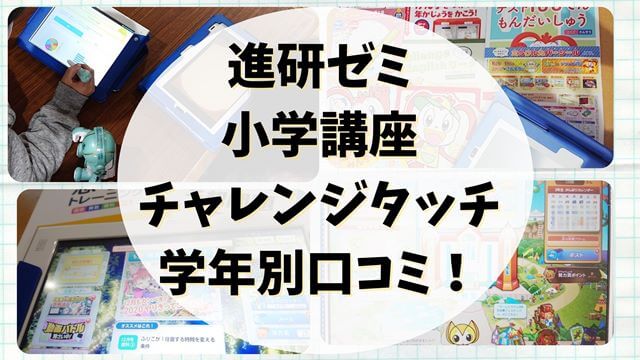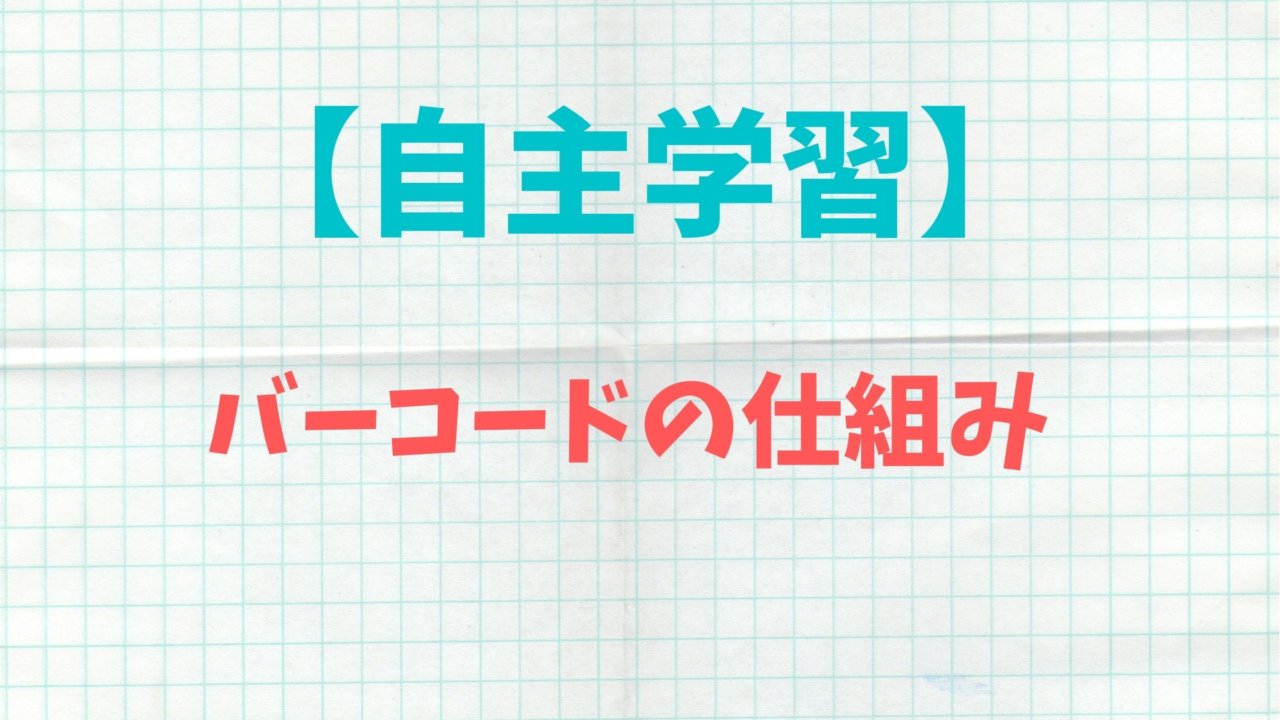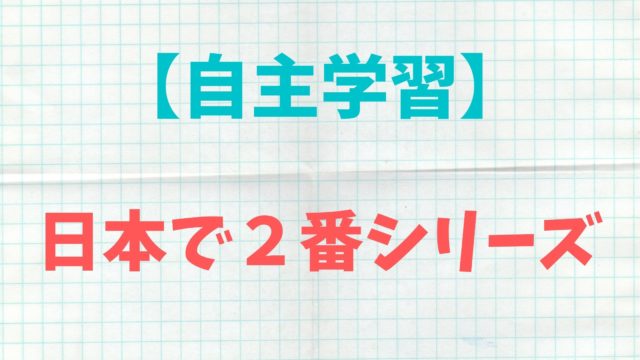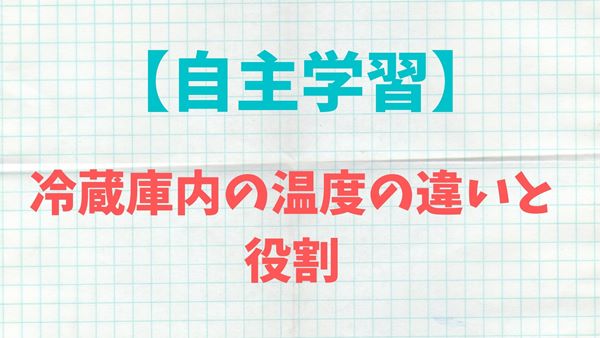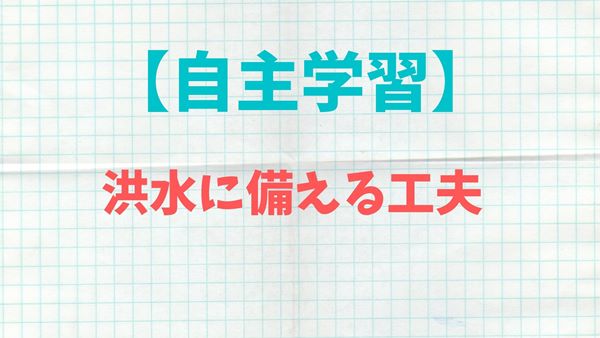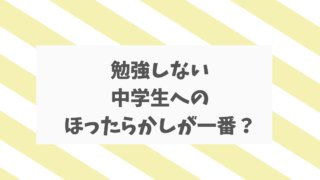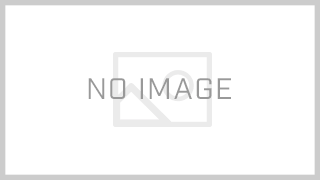そこで自主学習ネタとして、バーコードの仕組みについて紹介したいと思います。
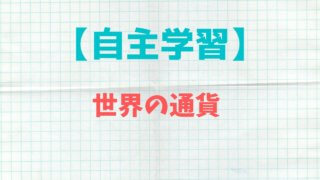
バーコードはなんのためにあるの?
バーコードがあることで、素早く商品の情報を読み取ることができ間違いを減らすことができます。
私たちの身近なところでバーコードが使われていると言えば、スーパーやコンビニですよね。
レジの時にバーコードをピッとしてもらうと思いますが、これが人の手で値段や商品の情報を一つ一つ入力しているとどうでしょう。
時間もかかるうえ間違いも多くでてきてしまいます。
そこで便利なのがバーコード!
バーコードがあれば値段や商品の情報を素早く読み取り間違いなく金額を計算することができます。
私たちが普段何気なくもらっているレシートも、素早く作る事がでるのはバーコードのおかげなんですよ。
また私たちの買い物が便利になるだけでなく、他にもバーコードは様々な場所で使われています。
商品の在庫や売上の管理、病院で患者さんや薬の管理、物流の現場で荷物の管理など様々な場面で大活躍しているのです。
バーコードの歴史!いつどこでできたの?
バーコードは1949にアメリカでモールス信号をもとに研究が始まりました。
アメリカのスーパーでレジの行列を解消するために、商品の情報を簡単に素早く読み取る手立てはないかと研究が始まったのです。
そして1952年に特許認定を取得する事ができました。
この特許を取得したバーコードは、後にアメリカで共通のバーコードとして使われるようになっていきます。
1967年にはアメリカのスーパーマーケットで実用化されました。
このアメリカで開発されたバーコードは世界へと広まっていき、ヨーロッパでさらに開発がすすめられます。
そして日本には、このヨーロッパで開発されたバーコードがやってくるのです。
日本ではまず1972年に大手百貨店の三越とダイエーで試しに導入されました。
しかしこの時は残念なことにすぐ普及とはいかなかったのです。
なぜすぐに普及していかなかったかと言うと、それはバーコードを商品に付けるのが予想以上に手間だったからです。
しかし、当時の通産省が先導して1978年に日本独自規格のバーコードをつくり出しました。
その4年後にあのコンビニチェーンのセブンイレブンがPOSを導入する際にネックとなっていたバーコードの貼り付けを求めたことで、バーコードは日本でも普及していくようになったのです。
バーコードの仕組み
バーコードをよく見ていただくとわかると思いますが、あの黒と白のシマシマの線は太さが異なっています。
バーコードの線は太さがそれぞれ違い、その組み合わせによって商品のデータがわかるようになっているのです。
ではバーコードの仕組みは具体的にどのようなっているのか見ていきましょ。
日本で使われているバーコードには黒白の線の下に13桁の番号が記載されています。
ここから商品の情報を読み取る事ができるのです。
例えば、「45 12345 67890 7 」というバーコードがあったとします。
最初の2桁、ここでは45 は、どこの国かを表しています。
ちなみに日本は45または49です。
手元にバーコードが付いたものがあったら見てみてください。
日本のものだったら45か49から始まっているはずですよ。
次のブロック12345は企業コードです。
どこの企業の商品なのかここから読み取る事ができます。
このように企業コードがあるため、バーコードの番号は好きなように付けることはできません。
きちんと申請を出して付けられているのです。
3つ目のブロック67890の部分は商品コードとなっており、どんな商品なのか読み取れます。
ここから商品名はもちろん、サイズやカラーなどがわかるようになっているのです。
そして最後の一桁7の部分はチェックデジットと言いって、バーコードを読み取った際に間違いがないか確認するためについています。
この数字は何でもよいというわけではなく、決まった計算の方法があるのです。
偶数桁の和×2+奇数桁の和=X
X÷9=◯余りY
9−Y=チェックデジットの数字
なので例えば今回の「45 12345 67890 7」のバーコードの場合は次のように計算されます。
29×2+25=83
83÷9=9余り2
9−2=7
このようにバーコードは付けられています。
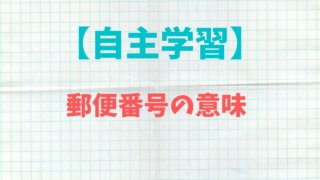
自主学習ネタ/バーコードの仕組みまとめ
自主学習ネタとしてバーコードの仕組みを紹介しました。
- バーコードはものの情報を素早く正確に読み取ることで手間やミスを減らすことができる。
- バーコードは13桁の番号で国・企業・商品情報を読み取る事ができる。
私たちの身近にある小さなバーコードには、様々な情報が詰まっています。
その情報を素早く正しく読み取る事で、私たちはスムーズに間違いなくサービスをうけたり仕事ができるのですね。