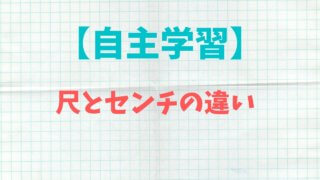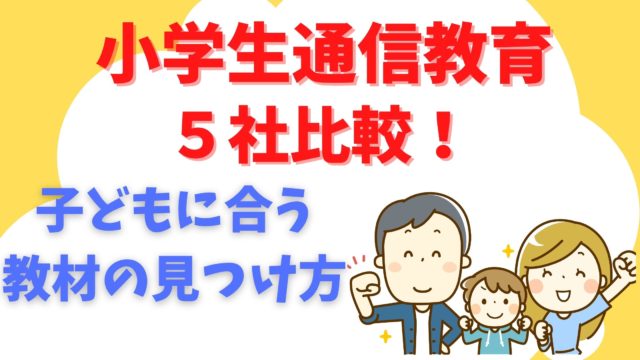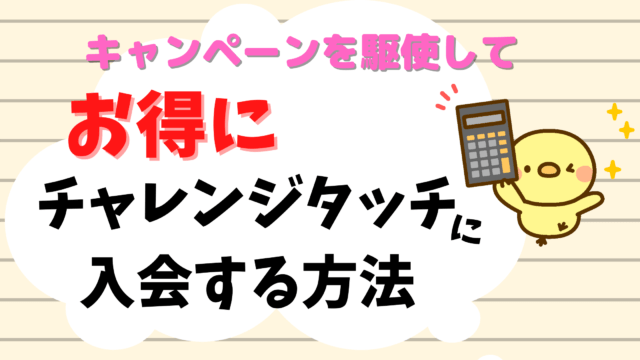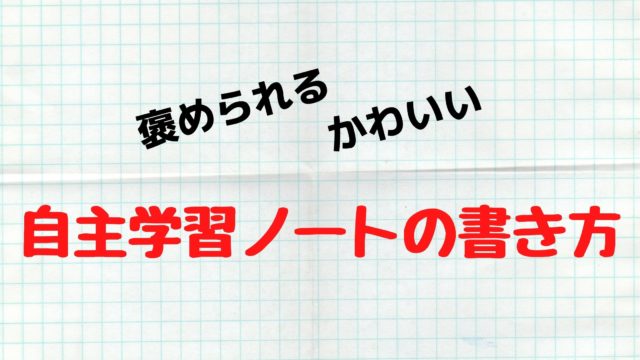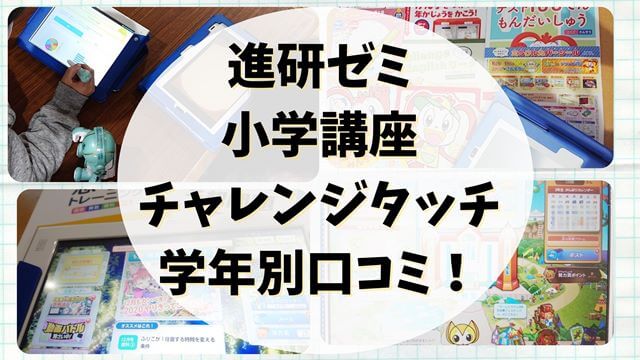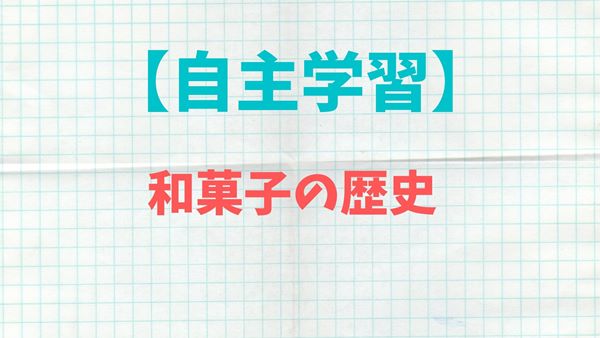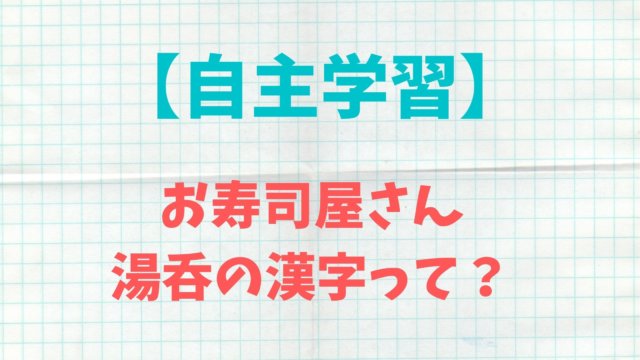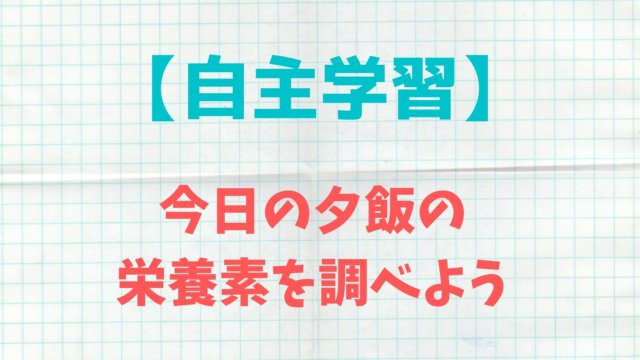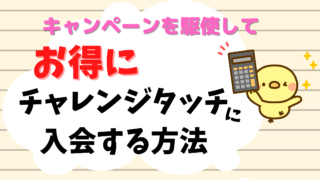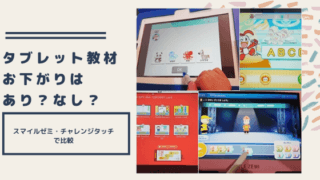お寿司屋では他では見かけない漢字が使われていたりして非常に興味がそそられます。
今回はきっと誰もが少し気になっているのではないかと思われる「寿司」と「鮨」の違いについてご紹介します。
小学生の自主学習のテーマにすると少し変わっていて面白いと思いますので、ぜひ最後までチェックしてみてください♪
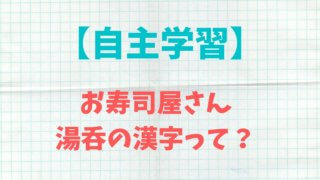
「寿司」と「鮨」の違いとは?
【鮨について】
「寿司」と「鮨」という漢字の方が歴史は長く、中国で魚を塩辛く漬けたものという意味で使われていました。それが日本に伝わり、現在では魚とお米を使った和食の定番でもある「すし」を表すようになりました。現在では一般的に江戸前のお寿司屋などで「握り鮨」などと使われていることが多いです。
【寿司について】
「寿司」は寿(ことぶき)を司る(つかさどる)と書きます。見るからに縁起が良い漢字が使われていますね。こちらは新鮮な魚と貴重なお米を使った「すし」が身分の高い朝廷などに献上したり、祭事に食べられる特別なものだったことから、このような縁起が良い字を使うようなったと考えられています。私たちが普段の生活の中で良く見かけるのもこちらの字が多いと思います。この字は「握り寿司」「ちらし寿司」「手巻き寿司」など色々なお寿司の名前で使われていますね。
さらに3つめの「鮓」という字もある!
【鮓について】
実は「すし」を表す字として、「鮓」という漢字もあるのを知っていますか?「鮓」「鮨」「寿司」の3つの字の中で「鮓」の字は一番古くから使われていて、もともとは魚とお米を発酵させた保存食のことを表していました。現在でも主に関西地方などで食べられている「熟れ鮓(なれずし)」「鮒鮓(ふなずし)」などにこの字が使われています。あまり見かけない字ですが、ぜひ覚えておきましょう!
自主学習ネタ/『寿司』と『鮨』の違い まとめ
「寿司」と「鮨」、さらに「鮓」の違いについて何となく分かりましたでしょうか?同じような意味を持つ漢字でも、詳しく調べてみると使われ出した時代が違ったり、歴史的な背景が関係していたりすることが分かって興味深いですね♪